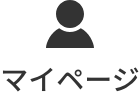新着情報

秋冬コンプレッションインナーって本当に暖かいの?
コンプレッションウェアは、今やスポーツやアウトドアの分野だけでなく、ワーカーの必須アイテムとしてもすっかり定着しました。速乾性が高いため汗をかく作業でも作業環境を快適に保てるほか、適度な締め付けによって体への負担が軽減されるなど高い機能性誇る点も人気の理由です。 そんなコンプレッションウェアですが、そのイメージから夏場に向けたインナーアイテムという印象が強いという人も多いと思いますが、そのイメージとは裏腹に、秋冬用のコンプレッションウェアというのも登場しています。 今回はその秋冬用コンプレッションウェアに注目し、夏用のコンプレッションウェアとの違いは何か? 真冬に着用すると本当に暖かいのか? など、気になる点を詳細に解説していきます。 :秋冬用のコンプレッションウェアとは 夏用のイメージが強いコンプレッションウェアですが、夏に着用する春夏用のほかにも秋冬用も存在します。また年間を通して着用できるオールシーズン対応のタイプも販売されています。 :春夏用と秋冬用の違い 春夏用のコンプレッションウェアも秋冬用のコンプレッションウェアも、体にフィットして適度な締め付けから体の動きをサポートし、体にかかる負担を軽減してくれるなどの基本的な機能は同じです。 では何が大きく異なるのかというと、それは使用されている素材の種類や厚みです。春夏用は冷涼感を得られやすいような素材が使用されている場合も少なくなく、また汗のかきやすい箇所の通気性をアップさせていたりなど、暑さに対して快適さを追求した工夫が施されています。 秋冬用のコンプレッションウェアでは、春夏用のような冷涼感を得られるような素材は不要です。逆に保温のために厚みのある生地が使用されていたりします。ただし、生地が厚いからといって蒸れやすいのかといえば決してそういうわけではなく、十分な通気性が確保されているのも特徴です。 :秋冬用のコンプレッションウェアは本当に暖かい? では最大の疑問である、「秋冬用のコンプレッションウェアは本当に暖かいのか?」の疑問について考えていきましょう。 :真冬は重ね着をしないと寒さに耐えられない 秋冬用のコンプレッションウェアが暖かいか否かは、着用時期によって異なります。当然、まだ暖かさの残る秋であれば秋冬用のコンプレッションウェア1枚だけで過ごすことは可能ですが、真冬の屋外となるとさすがに重ね着をしなければ寒さに耐えることはできません。 そもそもコンプレッションウェアはインナーとして着用するものでもありますので、適切なレイヤーで重ね着をしつつ寒さ対策を行えば、「秋冬用の暖かいインナー」としての保温機能を存分に発揮してくれます。 :秋冬用コンプレッションウェアの選び方 秋冬用コンプレッションウェアの選び方として最も重要なポイントは、ずばり「秋冬用が売られている時期に購入すること」です。 :春夏用では快適性が損なわれてしまう 「夏に購入したものがあるからそれを着用すればいいや」と考えたくもなりますが、先述のように春夏用と秋冬用とではコンプレッションウェアに使用されている素材や生地が異なります。 異なる季節のコンプレッションウェアを着用することによってインナーとしての快適性が損なわれてしまいますし作業効率低下に繋がってしまう可能性もあるので注意したいところです。 :秋冬用はできるだけ高機能なものを選ぶ 秋冬用コンプレッションウェアを選ぶ際に重視すべき点は、保温性と通気性です。寒い屋外で作業をするとはいえ、それなりに体を動かさなくてはならない場合にも備えなくてはなりません。 保温性ばかりが高くでも内部が蒸れてしまいますし、通気性が高くても保温性に乏しければ秋冬用インナーとしての意味がありません。どちらも体を冷やして体調を崩してしまう原因にもなってしまいます。 秋冬用コンプレッションウェアは、保温性に優れていながら通気性にもこだわった高機能なタイプを率先して選ぶようにするのがおすすめです。 :まとめ...
秋冬コンプレッションインナーって本当に暖かいの?
コンプレッションウェアは、今やスポーツやアウトドアの分野だけでなく、ワーカーの必須アイテムとしてもすっかり定着しました。速乾性が高いため汗をかく作業でも作業環境を快適に保てるほか、適度な締め付けによって体への負担が軽減されるなど高い機能性誇る点も人気の理由です。 そんなコンプレッションウェアですが、そのイメージから夏場に向けたインナーアイテムという印象が強いという人も多いと思いますが、そのイメージとは裏腹に、秋冬用のコンプレッションウェアというのも登場しています。 今回はその秋冬用コンプレッションウェアに注目し、夏用のコンプレッションウェアとの違いは何か? 真冬に着用すると本当に暖かいのか? など、気になる点を詳細に解説していきます。 :秋冬用のコンプレッションウェアとは 夏用のイメージが強いコンプレッションウェアですが、夏に着用する春夏用のほかにも秋冬用も存在します。また年間を通して着用できるオールシーズン対応のタイプも販売されています。 :春夏用と秋冬用の違い 春夏用のコンプレッションウェアも秋冬用のコンプレッションウェアも、体にフィットして適度な締め付けから体の動きをサポートし、体にかかる負担を軽減してくれるなどの基本的な機能は同じです。 では何が大きく異なるのかというと、それは使用されている素材の種類や厚みです。春夏用は冷涼感を得られやすいような素材が使用されている場合も少なくなく、また汗のかきやすい箇所の通気性をアップさせていたりなど、暑さに対して快適さを追求した工夫が施されています。 秋冬用のコンプレッションウェアでは、春夏用のような冷涼感を得られるような素材は不要です。逆に保温のために厚みのある生地が使用されていたりします。ただし、生地が厚いからといって蒸れやすいのかといえば決してそういうわけではなく、十分な通気性が確保されているのも特徴です。 :秋冬用のコンプレッションウェアは本当に暖かい? では最大の疑問である、「秋冬用のコンプレッションウェアは本当に暖かいのか?」の疑問について考えていきましょう。 :真冬は重ね着をしないと寒さに耐えられない 秋冬用のコンプレッションウェアが暖かいか否かは、着用時期によって異なります。当然、まだ暖かさの残る秋であれば秋冬用のコンプレッションウェア1枚だけで過ごすことは可能ですが、真冬の屋外となるとさすがに重ね着をしなければ寒さに耐えることはできません。 そもそもコンプレッションウェアはインナーとして着用するものでもありますので、適切なレイヤーで重ね着をしつつ寒さ対策を行えば、「秋冬用の暖かいインナー」としての保温機能を存分に発揮してくれます。 :秋冬用コンプレッションウェアの選び方 秋冬用コンプレッションウェアの選び方として最も重要なポイントは、ずばり「秋冬用が売られている時期に購入すること」です。 :春夏用では快適性が損なわれてしまう 「夏に購入したものがあるからそれを着用すればいいや」と考えたくもなりますが、先述のように春夏用と秋冬用とではコンプレッションウェアに使用されている素材や生地が異なります。 異なる季節のコンプレッションウェアを着用することによってインナーとしての快適性が損なわれてしまいますし作業効率低下に繋がってしまう可能性もあるので注意したいところです。 :秋冬用はできるだけ高機能なものを選ぶ 秋冬用コンプレッションウェアを選ぶ際に重視すべき点は、保温性と通気性です。寒い屋外で作業をするとはいえ、それなりに体を動かさなくてはならない場合にも備えなくてはなりません。 保温性ばかりが高くでも内部が蒸れてしまいますし、通気性が高くても保温性に乏しければ秋冬用インナーとしての意味がありません。どちらも体を冷やして体調を崩してしまう原因にもなってしまいます。 秋冬用コンプレッションウェアは、保温性に優れていながら通気性にもこだわった高機能なタイプを率先して選ぶようにするのがおすすめです。 :まとめ...

防寒着のサイズ選びのポイント
防寒着はその特性上厚みのある見た目になっているため、サイズ選びに迷ってしまうという人も意外と多いようです。 防寒着は通常の衣服と同じサイズで選んでも問題ないのか、それとも少し大きめのサイズを選ぶべきか、はたまた小さめを選んだ方がいいのか――。 今回、そんな防寒着選びに悩む人のために、選び方のポイントについてご紹介していきます。 :防寒着選びのポイント 一口に防寒着と言っても非常に幅広いのが特徴です。衣服の下に身に付ける秋冬用のインナーもそうですし、インナーとアウターとの間に身に付けるミドルレイヤー、そしてブルゾンやコートなどのアウターも防寒着です。防寒着選びは、少なくともこの3種類を意識して行わなければなりません。 :アウターの下に何を着るかによって選ぶ 最近は、インナーとしてコンプレッションウェアを着用する傾向が多く見られますし、それがスタンダードタイプとなりつつあります。体にフィットして適度な圧力を加えることで作業時の負担軽減が見込める機能的なインナーとして注目されています。 その上に着るミドルレイヤーは、通常の衣服と同様に自身に合ったサイズを選べば問題ありません。インナーが体にフィットしているからといってわざわざ小さいサイズを選び、ミドルレイヤーまで無理矢理体にフィットさせなくても大丈夫です。 一方、アウターについてはその下に何を着るかに応じて決めるのがベストです。下に着込むレイヤーが厚手のものであればサイズをワンランク上げた方がいいかもしれませんし、比較的薄着なら通常のサイズで選んでも問題ないでしょう。そのあたりはケースバイケースで対応するのがベストです。 :伸縮性の有無を重視して選ぶ 防寒着のうち、インナーやミドルレイヤーについてある程度伸縮性に富んだタイプのものを選んでおくと安心です。屋外で作業をするワーカーにとって動きやすさは非常に大切な要素です。 伸縮性の悪い素材のものを選んでしまうと動きやすさが阻害されてストレスを感じてしまい、快適さが奪われてしまいますので、生地の伸縮性にはこだわっておいて損はありません。 :タイトなサイズ感で作られたものもあるので注意 近年はスタイルを良く見せるため、敢えてタイトなデザインで作られているアウターが増えています。 そういったアウターは通常のサイズを選んでも少しきつめのサイズとなっているため、厚手のインナーやミドルレイヤーを着る場合には注意が必要です。 せっかく購入しても窮屈で動きづらいなどということにならないためにも、タイトなデザインのアウターを購入する際は通常のサイズよりも大きいものを選ぶようにするといいでしょう。 :防寒着を選ぶ際の注意点 防寒着を選ぶ際の注意点としてサイズを間違わないことはもちろんですが、それ以外にも意識しておきたいポイントがあります。 まず、アウターはできれば試着してから購入することが望ましいですし、作業をするのに合っていない防寒着を着るのもおすすめできません。 :アウターはなるべく試着してから購入するのが安心 先にも触れましたが、アウターはその下に何を着るかによって選ぶべきサイズを調整する必要が生じます。できれば試着をしてサイズ感をしっかりと確認してから購入した方が安心です。 :作業用に着用することを意識する 作業用に防寒着を購入するなら、必ず作業用に作られているものを選びましょう。デザイン性にこだわるあまり作業用とはかけ離れたものを選んでしまうと、耐久性が低くてすぐに着られなくってしまうことも考えられます。 また防水性や透湿性などが低くて快適性が奪われてしまう可能性もありますので、作業用に着用するのであれば作業用に作られた高機能なタイプを率先して選びましょう。...
防寒着のサイズ選びのポイント
防寒着はその特性上厚みのある見た目になっているため、サイズ選びに迷ってしまうという人も意外と多いようです。 防寒着は通常の衣服と同じサイズで選んでも問題ないのか、それとも少し大きめのサイズを選ぶべきか、はたまた小さめを選んだ方がいいのか――。 今回、そんな防寒着選びに悩む人のために、選び方のポイントについてご紹介していきます。 :防寒着選びのポイント 一口に防寒着と言っても非常に幅広いのが特徴です。衣服の下に身に付ける秋冬用のインナーもそうですし、インナーとアウターとの間に身に付けるミドルレイヤー、そしてブルゾンやコートなどのアウターも防寒着です。防寒着選びは、少なくともこの3種類を意識して行わなければなりません。 :アウターの下に何を着るかによって選ぶ 最近は、インナーとしてコンプレッションウェアを着用する傾向が多く見られますし、それがスタンダードタイプとなりつつあります。体にフィットして適度な圧力を加えることで作業時の負担軽減が見込める機能的なインナーとして注目されています。 その上に着るミドルレイヤーは、通常の衣服と同様に自身に合ったサイズを選べば問題ありません。インナーが体にフィットしているからといってわざわざ小さいサイズを選び、ミドルレイヤーまで無理矢理体にフィットさせなくても大丈夫です。 一方、アウターについてはその下に何を着るかに応じて決めるのがベストです。下に着込むレイヤーが厚手のものであればサイズをワンランク上げた方がいいかもしれませんし、比較的薄着なら通常のサイズで選んでも問題ないでしょう。そのあたりはケースバイケースで対応するのがベストです。 :伸縮性の有無を重視して選ぶ 防寒着のうち、インナーやミドルレイヤーについてある程度伸縮性に富んだタイプのものを選んでおくと安心です。屋外で作業をするワーカーにとって動きやすさは非常に大切な要素です。 伸縮性の悪い素材のものを選んでしまうと動きやすさが阻害されてストレスを感じてしまい、快適さが奪われてしまいますので、生地の伸縮性にはこだわっておいて損はありません。 :タイトなサイズ感で作られたものもあるので注意 近年はスタイルを良く見せるため、敢えてタイトなデザインで作られているアウターが増えています。 そういったアウターは通常のサイズを選んでも少しきつめのサイズとなっているため、厚手のインナーやミドルレイヤーを着る場合には注意が必要です。 せっかく購入しても窮屈で動きづらいなどということにならないためにも、タイトなデザインのアウターを購入する際は通常のサイズよりも大きいものを選ぶようにするといいでしょう。 :防寒着を選ぶ際の注意点 防寒着を選ぶ際の注意点としてサイズを間違わないことはもちろんですが、それ以外にも意識しておきたいポイントがあります。 まず、アウターはできれば試着してから購入することが望ましいですし、作業をするのに合っていない防寒着を着るのもおすすめできません。 :アウターはなるべく試着してから購入するのが安心 先にも触れましたが、アウターはその下に何を着るかによって選ぶべきサイズを調整する必要が生じます。できれば試着をしてサイズ感をしっかりと確認してから購入した方が安心です。 :作業用に着用することを意識する 作業用に防寒着を購入するなら、必ず作業用に作られているものを選びましょう。デザイン性にこだわるあまり作業用とはかけ離れたものを選んでしまうと、耐久性が低くてすぐに着られなくってしまうことも考えられます。 また防水性や透湿性などが低くて快適性が奪われてしまう可能性もありますので、作業用に着用するのであれば作業用に作られた高機能なタイプを率先して選びましょう。...

工事用ヘルメットとは〜工事用ヘルメットの選び方
ヘルメットには、工事用以外にもバイク用や災害用などさまざまなヘルメットが販売されていますが、作業で使用するなら必ず工事用のものを選ばなければなりません。ここでは工事用ヘルメットの特徴や他のヘルメットとの違い、そして購入時の選び方などを解説していきます。 :工事用ヘルメットとは 作業時に装着する工事用ヘルメットとは、そもそもどのような機能を持ったヘルメットなのでしょうか。また、工事用ヘルメットと他の用途で使用するヘルメットにはどのような違いがあるのでしょうか。 :作業者の安全を守るためのヘルメット 工事用ヘルメットは、作業をする上での安全確保に配慮して設計されたヘルメットのことです。 例えばバイク用のヘルメットの場合、転倒や衝突による事故から頭部を保護することを目的に作られています。 一方、工事用の場合も頭部を保護する目的である点は同じですが、転倒や衝突以外にも、頭上からの落下物や飛来物などからの衝撃にも備えた設計になっているのが特徴です。 さらに、電気工事時に感電を防ぐ目的で装着するヘルメットもあるなど、一般的なヘルメットに比べてより安全性の高い機能を備えているのも工事用ヘルメットの魅力です。 :さまざまな素材やデザインから選べる 工事用ヘルメットには、FRP(ファイバーグラス・レインフォースド・プラスチック)やPC(ポリカーボネート)、PE(ポリエチレン)、ABS(アクリロ二トリル・ブタジエン・スチレン)などさまざまな素材のものがありますし、デザインもツバ付きやツバなし、シールド付きやバイザー付きなどがあり、カラーバリエーションも豊富です。 一昔前とは違い、近年の工事用ヘルメットなら作業時の用途に合わせて、素材やデザイン、カラーなど幅広い選択肢からお好みに合わせて見つけることができます。 :工事用ヘルメットの選び方 作業に適したヘルメットだからとはいえ、工事用ヘルメットであればどんなヘルメットを選んでも大丈夫ということにはなりません。 作業内容はもちろんのこと、快適性にもこだわったヘルメット選びも必要です。 :作業内容に合わせて選ぶ どのような作業でヘルメットを装着するのかによって、使用すべきヘルメット選びも異なります。 例えば建設作業の現場なら、良好な視界確保のためにもツバ付きタイプやバイザータイプを選ぶのがおすすめですし、ぐらついて作業がしづらくならないためにジャストフィット機能に優れたものを選ぶのもおすすめです。 また電気工事に使用するなら、感電防止機能に優れた絶縁用ヘルメットを選ぶなど、それぞれの作業内容に応じたものを率先して選ぶ必要もあります。 :気候に合わせて選ぶ 近年では、通気性や遮熱性に優れた工事用ヘルメットの種類も増加しています。真夏の炎天下における作業が多いなら、熱中症対策としても有効です。 猛暑時におけるヘルメットの着用は不快感を伴いがちですので、工事用ヘルメットを選ぶ際の選択肢として快適性を追求してみるのもおすすめです。 :工事用ヘルメットを選ぶ際の注意点 工事用ヘルメットを選ぶ際には、ヘルメット自体の耐久年数や内装の種類、国家検定合格品であるかどうかなど、気を付けておきたい注意点もあります。 :ヘルメットの耐久年数に注意する これは選ぶ際の注意点というより購入後の注意点になりますが、工事用ヘルメットを購入したからといって永久に使い続けられるわけではありません。なぜなら、ヘルメットには耐久年数があるからです。 工事用ヘルメットの素材 耐久年数 主な特徴 FRP製 5年以内...
工事用ヘルメットとは〜工事用ヘルメットの選び方
ヘルメットには、工事用以外にもバイク用や災害用などさまざまなヘルメットが販売されていますが、作業で使用するなら必ず工事用のものを選ばなければなりません。ここでは工事用ヘルメットの特徴や他のヘルメットとの違い、そして購入時の選び方などを解説していきます。 :工事用ヘルメットとは 作業時に装着する工事用ヘルメットとは、そもそもどのような機能を持ったヘルメットなのでしょうか。また、工事用ヘルメットと他の用途で使用するヘルメットにはどのような違いがあるのでしょうか。 :作業者の安全を守るためのヘルメット 工事用ヘルメットは、作業をする上での安全確保に配慮して設計されたヘルメットのことです。 例えばバイク用のヘルメットの場合、転倒や衝突による事故から頭部を保護することを目的に作られています。 一方、工事用の場合も頭部を保護する目的である点は同じですが、転倒や衝突以外にも、頭上からの落下物や飛来物などからの衝撃にも備えた設計になっているのが特徴です。 さらに、電気工事時に感電を防ぐ目的で装着するヘルメットもあるなど、一般的なヘルメットに比べてより安全性の高い機能を備えているのも工事用ヘルメットの魅力です。 :さまざまな素材やデザインから選べる 工事用ヘルメットには、FRP(ファイバーグラス・レインフォースド・プラスチック)やPC(ポリカーボネート)、PE(ポリエチレン)、ABS(アクリロ二トリル・ブタジエン・スチレン)などさまざまな素材のものがありますし、デザインもツバ付きやツバなし、シールド付きやバイザー付きなどがあり、カラーバリエーションも豊富です。 一昔前とは違い、近年の工事用ヘルメットなら作業時の用途に合わせて、素材やデザイン、カラーなど幅広い選択肢からお好みに合わせて見つけることができます。 :工事用ヘルメットの選び方 作業に適したヘルメットだからとはいえ、工事用ヘルメットであればどんなヘルメットを選んでも大丈夫ということにはなりません。 作業内容はもちろんのこと、快適性にもこだわったヘルメット選びも必要です。 :作業内容に合わせて選ぶ どのような作業でヘルメットを装着するのかによって、使用すべきヘルメット選びも異なります。 例えば建設作業の現場なら、良好な視界確保のためにもツバ付きタイプやバイザータイプを選ぶのがおすすめですし、ぐらついて作業がしづらくならないためにジャストフィット機能に優れたものを選ぶのもおすすめです。 また電気工事に使用するなら、感電防止機能に優れた絶縁用ヘルメットを選ぶなど、それぞれの作業内容に応じたものを率先して選ぶ必要もあります。 :気候に合わせて選ぶ 近年では、通気性や遮熱性に優れた工事用ヘルメットの種類も増加しています。真夏の炎天下における作業が多いなら、熱中症対策としても有効です。 猛暑時におけるヘルメットの着用は不快感を伴いがちですので、工事用ヘルメットを選ぶ際の選択肢として快適性を追求してみるのもおすすめです。 :工事用ヘルメットを選ぶ際の注意点 工事用ヘルメットを選ぶ際には、ヘルメット自体の耐久年数や内装の種類、国家検定合格品であるかどうかなど、気を付けておきたい注意点もあります。 :ヘルメットの耐久年数に注意する これは選ぶ際の注意点というより購入後の注意点になりますが、工事用ヘルメットを購入したからといって永久に使い続けられるわけではありません。なぜなら、ヘルメットには耐久年数があるからです。 工事用ヘルメットの素材 耐久年数 主な特徴 FRP製 5年以内...

空調服とは〜空調服の選び方
ここ数年、一気に注目度がアップしてきた作業服の一つに「空調服」があります。文字通り空調機能を備えた作業服ですが、そもそもなぜそれほどの人気を集めているのか? そして空調機能が付帯していることでどんなメリットがあるのか? 詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。 空調服ってどういうもの? 近年の夏は、猛暑や酷暑という言葉が当たり前になるほど、毎年のように記録的な暑さに見舞われています。 それと同時に、空調服という言葉も耳にする機会が増えていますが、そもそも空調服とはどのようなものなのでしょうか。詳しくご説明していきます。 :空調機能搭載の作業服 空調服は、文字どおり「空調機能が付帯した作業服」のことで、衣服内の空調機能を上げることによって快適に作業できるのが特徴です。衣服内の空気を調整することによって真夏の熱中症対策に有効な作業服として近年人気を集めています。 空調服と聞くと少々物々しいイメージを抱いてしまいますが、一般的には「ファン付き作業服」や「ファン付きウエア」などと呼ばれていますので、そちらの呼称なら馴染みがあるという方も少なくないでしょう。 :猛暑が当たり前の夏に有効 空調服の最大のメリットは「猛暑の夏に有効」という点です。内蔵されたファンによって衣服内に空気が取り込まれ、高温になった衣服内を涼しく保ってくれます。 真夏でもエアコンのない屋外での作業を余儀なくされている作業員にとっては、まさに着るだけで涼しくなる画期的な作業服なのです。 :屋外作業だけでなく趣味でも大活躍 また、屋外での仕事だけではなく趣味でも重宝できるのが魅力です。特にキャンプや登山、釣りなどのアウトドアを中心に大活躍してくれます。 :空調服で涼しくなる仕組み 衣服の中に外気を強制的に取り込むことで涼しくなる空調服ですが、真夏なら外気も相当熱を持っているはずです。 それなのになぜ、高熱の外気を取り込むだけで作業服内が快適になるのでしょうか。その仕組みをご紹介します。 :気化熱の原理を応用 40℃前後と高熱のはずの外気を空調服内に送り込むだけで涼しく感じるのは、人間の生理現象を上手に活かしているからです。それが「気化熱」と呼ばれるものです。 人の体は暑さで高熱になると、体内の温度を下げるために汗を出し、汗が蒸発することで体の熱を下げる機能を備えていますが、空調服はこの原理を応用しています。 作業服内に風を送り込むことで汗が蒸発し、それが気化熱となって体を冷やしてくれるため涼しく快適な環境が保たれる仕組みなのです。 :空調服の選び方 真夏の作業には空調服が向いているとはいえ、空調服なら何でもOKというわけではありません。空調服にもさまざまなタイプがありますので、できるだけ作業内容に合ったタイプの空調服を選ぶのがおすすめです。 :高所作業が多い人向けの空調服 高所作業をされる作業員向けに、高所作業向けハーネスに対応した空調服もあります。とび職や大工ほか、足場の施工作業など炎天下で高所作業をする人のために作られた空調服です。長袖と合わせて半袖タイプを選ぶこともできます。 :動きやすさにこだわる人向けの空調服 低所での作業が中心で動きやすさを重視したい人には半袖タイプの空調服が定番になっています。デザインも比較的豊富なためカジュアルなタイプを好む人にもおすすめ度が高めですし、高所作業用と比べてコスト面でも安価なのが特徴です。 :アウトドアなど趣味で使いたい人向けの空調服 キャンプや釣りなどアウトドアを楽しむ人から人気なのがベストタイプの空調服です。空調服の中で最も手軽に着用できるタイプで、普段着として着用している人も少なくありません。 :空調服をECサイトで購入するメリット 空調服の購入先は、実店舗かECサイトなどを利用したネット通販が主流ですが、メリットが大きいのはECサイトでの購入です。 :品揃えが豊富で好きな時に買える...
空調服とは〜空調服の選び方
ここ数年、一気に注目度がアップしてきた作業服の一つに「空調服」があります。文字通り空調機能を備えた作業服ですが、そもそもなぜそれほどの人気を集めているのか? そして空調機能が付帯していることでどんなメリットがあるのか? 詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。 空調服ってどういうもの? 近年の夏は、猛暑や酷暑という言葉が当たり前になるほど、毎年のように記録的な暑さに見舞われています。 それと同時に、空調服という言葉も耳にする機会が増えていますが、そもそも空調服とはどのようなものなのでしょうか。詳しくご説明していきます。 :空調機能搭載の作業服 空調服は、文字どおり「空調機能が付帯した作業服」のことで、衣服内の空調機能を上げることによって快適に作業できるのが特徴です。衣服内の空気を調整することによって真夏の熱中症対策に有効な作業服として近年人気を集めています。 空調服と聞くと少々物々しいイメージを抱いてしまいますが、一般的には「ファン付き作業服」や「ファン付きウエア」などと呼ばれていますので、そちらの呼称なら馴染みがあるという方も少なくないでしょう。 :猛暑が当たり前の夏に有効 空調服の最大のメリットは「猛暑の夏に有効」という点です。内蔵されたファンによって衣服内に空気が取り込まれ、高温になった衣服内を涼しく保ってくれます。 真夏でもエアコンのない屋外での作業を余儀なくされている作業員にとっては、まさに着るだけで涼しくなる画期的な作業服なのです。 :屋外作業だけでなく趣味でも大活躍 また、屋外での仕事だけではなく趣味でも重宝できるのが魅力です。特にキャンプや登山、釣りなどのアウトドアを中心に大活躍してくれます。 :空調服で涼しくなる仕組み 衣服の中に外気を強制的に取り込むことで涼しくなる空調服ですが、真夏なら外気も相当熱を持っているはずです。 それなのになぜ、高熱の外気を取り込むだけで作業服内が快適になるのでしょうか。その仕組みをご紹介します。 :気化熱の原理を応用 40℃前後と高熱のはずの外気を空調服内に送り込むだけで涼しく感じるのは、人間の生理現象を上手に活かしているからです。それが「気化熱」と呼ばれるものです。 人の体は暑さで高熱になると、体内の温度を下げるために汗を出し、汗が蒸発することで体の熱を下げる機能を備えていますが、空調服はこの原理を応用しています。 作業服内に風を送り込むことで汗が蒸発し、それが気化熱となって体を冷やしてくれるため涼しく快適な環境が保たれる仕組みなのです。 :空調服の選び方 真夏の作業には空調服が向いているとはいえ、空調服なら何でもOKというわけではありません。空調服にもさまざまなタイプがありますので、できるだけ作業内容に合ったタイプの空調服を選ぶのがおすすめです。 :高所作業が多い人向けの空調服 高所作業をされる作業員向けに、高所作業向けハーネスに対応した空調服もあります。とび職や大工ほか、足場の施工作業など炎天下で高所作業をする人のために作られた空調服です。長袖と合わせて半袖タイプを選ぶこともできます。 :動きやすさにこだわる人向けの空調服 低所での作業が中心で動きやすさを重視したい人には半袖タイプの空調服が定番になっています。デザインも比較的豊富なためカジュアルなタイプを好む人にもおすすめ度が高めですし、高所作業用と比べてコスト面でも安価なのが特徴です。 :アウトドアなど趣味で使いたい人向けの空調服 キャンプや釣りなどアウトドアを楽しむ人から人気なのがベストタイプの空調服です。空調服の中で最も手軽に着用できるタイプで、普段着として着用している人も少なくありません。 :空調服をECサイトで購入するメリット 空調服の購入先は、実店舗かECサイトなどを利用したネット通販が主流ですが、メリットが大きいのはECサイトでの購入です。 :品揃えが豊富で好きな時に買える...

作業服とは〜作業服の選び方
一昔前と比べ、現在では普段着として作業服を取り入れるファッションも流行するなど、作業服を取り巻くイメージも大きく変化しています。 しかし本来はファッション性に重点を置くのではなく、働く者が作業しやすいように効率性を考えて作られているものこそが「本物の作業服」なのです。 ここでは、そもそも作業服の定義とは何か? おすすめの選び方はあるのか? などについて解説していきます。 :作業服とは 近年、そのファッション性が注目され普段着としても人気を集めている作業服ですが、本来は働く人が仕事をしやすいよう、さまざまな作業に合わせ効率性を考えて作られているのが特徴です。 :作業のために作られた衣服 ファッション性を追求し、普段着として気軽に着用できる作業服は、正確に言えば「作業服風の衣服」といったイメージです。 本来の作業服とは、作業をする者が安全かつ効率的に仕事ができる点に主眼を置き、機能性や動作性にも優れた衣服のことを指します。 生地が丈夫であることや通気性に優れていること、速乾性に優れていることなど、作業内容に合わせて選ぶことができる点も作業服の魅力です。 :さまざまな職業の制服として人気が高い 建築業や土木業、製造業、運輸業などなど、作業服はさまざまな職業を見分ける目安にもなっています。実際、着用している作業服を見ればどのような職業に従事しているのかをすぐに判別できます。 また、作業服に社名を入れ、社内全体で統一したユニフォームとして導入している企業も少なくありません。 :自分に合った作業服の選び方 作業服の選び方は企業や個人によってこだわるべきポイントが異なります。企業であれば企業イメージを共有できるものが望ましいでしょうし、個人であれば職種に合った機能を意識して選ぶのがおすすめです。 :企業イメージを共有できるもの 企業として作業服を選ぶなら、できるだけ統一感の出るような作業服を選ぶと一体感が出て作業意識の向上も期待できます。 同じデザインであることはもちろんのこと、社名やロゴを入れたものや同じカラーの作業服で統一するのもいいでしょう。 また、従業員ごとに名前の刺繍を入れたり、個人ごとのパーソナルカラーを取り入れたりして個性を出す方法もあります。 作業服のデザインやカラーを統一することで企業イメージを共有しやすくなりますし、個性を加えることで従業員一人一人のモチベーションアップも図れます。 :職種に合った機能を持ったもの 外仕事の多い建築・土木関係なら、防汚や撥水効果の高い素材が好ましいでしょうし、夏なら通気性や速乾性、冷感機能を備えた作業服を、冬なら保温性の高い作業服を選ぶ必要があります。 その他、精密機械に携わる作業がメインなら帯電防止機能にもこだわる必要がありますし、調理関係なら撥水や撥油性の高い作業服など、作業内容に見合ったものを使用するのが理想です。 何を目的とした作業なのか、作業をする場所はどこなのかなど、さまざまな要因を考慮して、最も機能性に優れた作業服を選ぶことが重要なポイントとなります。 :見た目から役割の分かるもの 例えば警備員さんなら、作業服を一目見るだけで人混みの中でも見分けられますし、交通誘導であれば自動車の運転手に対して交通規制が行われていることを瞬時に知らせることができます。 このように職種によっては社会的な要素によって他と差別化を図らなければならないケースもあります。その場合、「一目見てどのような役割を担った職に従事しているのか」がすぐに分かるような作業服を選ぶことが求められます。 :作業服をECサイトで購入するメリット 作業服の具体的な購入方法としては、主に実店舗での購入とネット通販での購入の2つに絞られますが、購入を検討するなら実店舗よりもECサイトがおすすめです。 :手間もかからず気軽に購入できる 作業服の購入方法としては、昔から作業服専門店などを利用する人の割合も多めです。しかし近くに店舗がない場合は購入に手間がかかってしまうこともある上に、売り切れだったりすると骨折り損になってしまう点がデメリットです。...
作業服とは〜作業服の選び方
一昔前と比べ、現在では普段着として作業服を取り入れるファッションも流行するなど、作業服を取り巻くイメージも大きく変化しています。 しかし本来はファッション性に重点を置くのではなく、働く者が作業しやすいように効率性を考えて作られているものこそが「本物の作業服」なのです。 ここでは、そもそも作業服の定義とは何か? おすすめの選び方はあるのか? などについて解説していきます。 :作業服とは 近年、そのファッション性が注目され普段着としても人気を集めている作業服ですが、本来は働く人が仕事をしやすいよう、さまざまな作業に合わせ効率性を考えて作られているのが特徴です。 :作業のために作られた衣服 ファッション性を追求し、普段着として気軽に着用できる作業服は、正確に言えば「作業服風の衣服」といったイメージです。 本来の作業服とは、作業をする者が安全かつ効率的に仕事ができる点に主眼を置き、機能性や動作性にも優れた衣服のことを指します。 生地が丈夫であることや通気性に優れていること、速乾性に優れていることなど、作業内容に合わせて選ぶことができる点も作業服の魅力です。 :さまざまな職業の制服として人気が高い 建築業や土木業、製造業、運輸業などなど、作業服はさまざまな職業を見分ける目安にもなっています。実際、着用している作業服を見ればどのような職業に従事しているのかをすぐに判別できます。 また、作業服に社名を入れ、社内全体で統一したユニフォームとして導入している企業も少なくありません。 :自分に合った作業服の選び方 作業服の選び方は企業や個人によってこだわるべきポイントが異なります。企業であれば企業イメージを共有できるものが望ましいでしょうし、個人であれば職種に合った機能を意識して選ぶのがおすすめです。 :企業イメージを共有できるもの 企業として作業服を選ぶなら、できるだけ統一感の出るような作業服を選ぶと一体感が出て作業意識の向上も期待できます。 同じデザインであることはもちろんのこと、社名やロゴを入れたものや同じカラーの作業服で統一するのもいいでしょう。 また、従業員ごとに名前の刺繍を入れたり、個人ごとのパーソナルカラーを取り入れたりして個性を出す方法もあります。 作業服のデザインやカラーを統一することで企業イメージを共有しやすくなりますし、個性を加えることで従業員一人一人のモチベーションアップも図れます。 :職種に合った機能を持ったもの 外仕事の多い建築・土木関係なら、防汚や撥水効果の高い素材が好ましいでしょうし、夏なら通気性や速乾性、冷感機能を備えた作業服を、冬なら保温性の高い作業服を選ぶ必要があります。 その他、精密機械に携わる作業がメインなら帯電防止機能にもこだわる必要がありますし、調理関係なら撥水や撥油性の高い作業服など、作業内容に見合ったものを使用するのが理想です。 何を目的とした作業なのか、作業をする場所はどこなのかなど、さまざまな要因を考慮して、最も機能性に優れた作業服を選ぶことが重要なポイントとなります。 :見た目から役割の分かるもの 例えば警備員さんなら、作業服を一目見るだけで人混みの中でも見分けられますし、交通誘導であれば自動車の運転手に対して交通規制が行われていることを瞬時に知らせることができます。 このように職種によっては社会的な要素によって他と差別化を図らなければならないケースもあります。その場合、「一目見てどのような役割を担った職に従事しているのか」がすぐに分かるような作業服を選ぶことが求められます。 :作業服をECサイトで購入するメリット 作業服の具体的な購入方法としては、主に実店舗での購入とネット通販での購入の2つに絞られますが、購入を検討するなら実店舗よりもECサイトがおすすめです。 :手間もかからず気軽に購入できる 作業服の購入方法としては、昔から作業服専門店などを利用する人の割合も多めです。しかし近くに店舗がない場合は購入に手間がかかってしまうこともある上に、売り切れだったりすると骨折り損になってしまう点がデメリットです。...